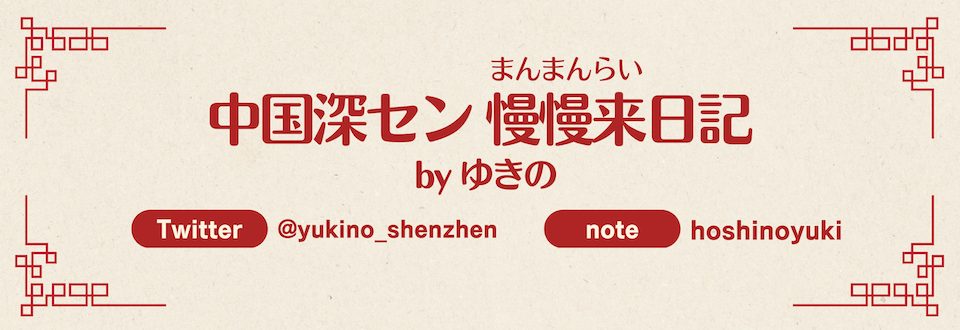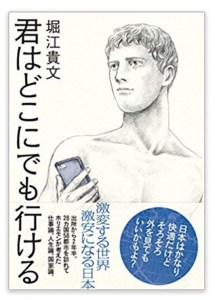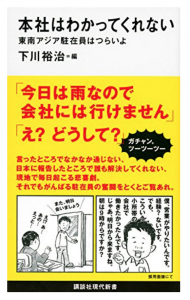海外で働く。
決意してみたけど、実際どうなんだろう? 危険なことが起きたり、騙されたりするんじゃ…
これまで経験したことがない、全く新しい環境で働くことや暮らすことは不安がいっぱいだと思います。
私の場合、「そうきたか!」「次は何が起きるんだろう」というワクワクが不安をいつも大きく上回っているので、些細なことは気になりません。
とはいえ、海外特有のしんどいことはいくつもあります。
今回は「アジア転職、やってみたいけどやっぱりなんか不安…」という方へ、ぜひ実体験による苦労エピソードをお届け。
海外在住のみなさまにとっては、ただのあるあるエピソードかも😂
だいたい、みんな、テキトー
役所での手続き、レストランでの対応、バスの運転手、職場の先輩…
数えたらキリがありませんが、ほとんどの人は適当で雑。
外国人居住登録を届けたら、登録されたパスポートの番号ちがって発行されたり
レストランでは、お客さんいない間はテーブルにどどんと座ってスマホに夢中になってたり。
バスの運転手は急ブレーキと急発進を繰り返すので、コントみたいに乗客が揺れまくってます。「昨日、なんか嫌なことあったんかな…」ってちょっと心配になるくらいの激しさ。
あと、とつぜん雨が降り出したりとか、夜10時以降とか、バスが全然来なくなります。
「来ないなあ」と思いながらぼーっとしたり、サクッとあきらめてタクシーに乗ります。
そして職場の先輩。転職して1ヶ月以内の頃は、「この業務はどうやったらいいですか?」と
いちいち確認してましたが、なにを聞いても「うん!いいよ!」って。
翌月からは「あれとあれとあれはこうやっておきました」みたいにまとめて事後報告に変えてたんですが、先輩の返事は「すごいね!完璧!」ほぼ変わらない。
いや、自由度高く仕事を任せてもらえるの好きなんですけど。
サービスを提供される側としては、日本のサービスが恋しくなることもよくある
まとめ:
アジア各国ではサービス業やインフラが適当。
適当さに慣れることや、こっちも適当になれるよう心の持ち方を体得することが大切。
現地スタッフとすれちがう
前述した先輩もそうなんですが、一緒に働くひとたちから毎日のようにサプライズをもらいます。
休憩時間はオフィス全消灯でお昼寝タイム
退勤30分前から丁寧に帰宅準備、そして5分前にドアの前でスタンバイ
「ちょっと頭が痛い…」って朝に電話してきて病休。
「親知らずが…」って電話してきて、その日から2週間のいきなり病休(親知らずの抜歯のあとは絶対安静らしい。ホントかな?)
「みんなで協力してがんばろう!」って団結した翌週に退職届、翌月にあっさり転職。
自分の意志がいちばん。自由度高く自己流すぎて、「ちょっとやり方変えてほしい」と何度お願いしても「No」
我慢の限界で大ゲンカしたら、翌日に退職届。
よくも悪くも、日本でいうところの「普通さあ…」「わかるよね?」といった共通理解がひとつもない。
働き始めたときは「自由だ!」って嬉しくなったけど、1年経ったら「もうちょっと、足並みそろえようよ…」って嘆いてた。
まとめ:
みんなちがってみんないい、周りなんて気にしない。でも雨が降ったらみんなまとめて遅刻する。
労働は悪。とにかくすぐに帰りたい。
優秀なのに働きたくないからトータル生産性イマイチなアジア人。
働きたいけど要領悪いからトータル生産性イマイチな日本人。
※個人差があります。
言葉がわからない
これもじわじわ不快を感じるポイント。
特にアジア諸国だと、韓国語、タイ語、ベトナム語、マレー語、インドネシア語などなど行く先々で言葉が違う。
メリットはバスや電車でのけたたましいおしゃべりがひとつも耳に入ってこないこと。
そしてデメリットは、レストランやタクシーで必要な最低限の会話すらできないこと。
ちなみに仕事だけは、日本語か英語でだいたいイケます。
なぜなら私達は現地語を話す要員ではなく、現地の日本顧客や日系企業にアプローチするために働くので。
語学力は求められていないことがほとんどです。
たまにローカルスタッフと簡単な現地語で話すとグッと距離が縮まることもあるけど、それで生産性が上がるわけではないし。
語学をゼロから自力で身につける。
「簡単だよ〜」と言う人は、ごく一部の語学センスがある人か優秀な人。
多くの凡人は、毎日コツコツ勉強して、半年から1年かけてやっと日常会話ができるくらい。
生活と仕事ができればいいから、現地語にはノータッチ、という現地採用の友人もいます。
私はローカルライフにフルコミットしたい派なので、中国語を毎日少しずつ勉強しています。
でも難しい…学校教育で基礎があったけど、30代でゼロから学ぶのは本当に難しい。
まとめ:
言葉がわからないことで、日常生活のささいなことに支障をきたすことも。
現地語を学びたくなるくらい魅力を感じる国や都市を選んでみたりするとか。
病院に行くと高額
日本に住んでる日本人なら、保険証を持って病院へ行けばだいたい3割負担、医療費は安い。
これが海外では医療はビジネスなので、病院や医師によって費用はさまざま、そして10割負担。
海外駐在員は海外保険に入っていて、家族まるごと高額な医療費はほぼ無料。
現地採用でも、ローカルクリニックなら会社負担で格安かほぼ無料で行ける。
ちょっとした風邪や発熱ならローカルクリニックでいいんですが、どうしても深刻な時、日本語が通じる超高級クリニックにかかりたい…
私にとっては、それが先月のことでした。どうしても頭痛に耐えられなくなって、高額を覚悟して行ってみたところ…
高かったー!!!
でもまあ、その後3日くらいでよくなったので、行ってよかったと思ってます。
健康は財産ですね。
まとめ:
費用が安くて高品質な日本の医療に比べて、海外では質も費用もバラバラ。
健康管理・自己管理を意識して、病院いらずの体づくりを。
油が多くて野菜が少ないローカルフード
またまた前述の健康管理とも重なるんですが、アジア諸国のローカルフードを食べ続けるといつか体を壊します。
屋台なんかもずらりと並んで、できたてをすぐに安く食べられるのはとても魅力的なんですが。


結局、ローカルフードって安く美味しく作るために、
砂糖・塩・油・炭水化物がたっぷりで、体に必要な栄養素は少ないらしいです。
そういう体に悪いものほど、脳は快楽を感じて「もっと!もっと食べたい!」となるんだとか。
人類の長い歴史において、肥満より飢餓のほうが死ぬリスクがずっと高かったので、私達の脳は餓死しないよう蓄えようと必死なんだそうです。
最近、ほぼ毎日見ている勝間和代さんのYoutubeチャンネルで学びました。
すぐに食べられるもので美味しく安く食事を済ませることは、短期的には幸せでも、中長期的に考えれば健康を損なうリスクが高くなる、ということ。
すべての外食は、消費者にできるだけたくさん消費してもらうために作られるんであって、消費者を健康に長生きさせるためにできているんじゃないんだなって思います。
そのための、低価格・砂糖・塩・油・炭水化物。
さらにアジア諸国は朝昼夜すべて外食が基本です。
家で食事をつくらない、つくるのがめんどくさくなる、という状況になりがち。
日本だったらコンビニで買って帰ったりするけど、屋台みたいに1食200円以下で満腹になることはないので、家で料理する人も結構います。
というわけで、日本にいるうちから基本的な自炊をラクに楽しくできるように実践するのがいいと思います。
炊飯器でお米を炊いて、お味噌をとかして乾燥わかめ入れるだけで十分です。
私も海外生活4年目にしてやっと自炊の練習を始めました。
まとめ:
安くて美味しいローカルフードはものすごく体に悪い。
適度に楽しんで、自炊中心の生活リズムを作るのが理想的。